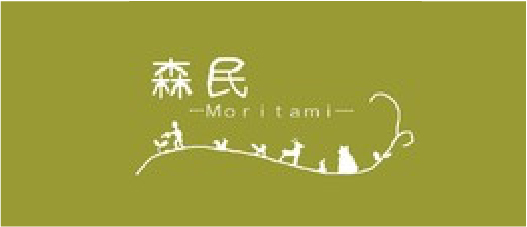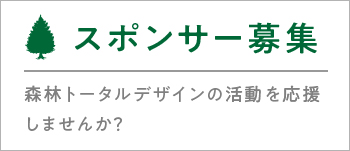– ロープワーク高所伐採技師 養成講座(概要) –
*ロープワーク高所伐採技師 養成講座内容の概要です。内容は都度変更することがあります。
高所伐採といえば、これまで神社仏閣等での需要が多かったですが、近年、木の成長や山の手入れ不足(間伐遅れ等)により、家の裏山や道路脇の危険木伐採、河川沿い、高速道路脇等の高所伐採の需要が増えてきています。
この技術は全国的に今後ますます必要とされるものになると思われ、技術者不足が予想されます。そこで今回、特に若手技術者に向けた高所伐採の講習会を開催させていただくことになりました。
この講習では、特殊な道具を使い、体型的に組み立てられたロープワークを中心とした高所伐採方法について解説、実技指導を行います。道具の選び方から、安全な道具の使い方、ロープワーク技術、見積り書の作り方や仕事の請け方まで、プロとして高所伐採を行っていくのに必要な技術と知識が学べます。 この技術は、ロープワークだけでなく、クレーンワークにも応用できます。また、高所伐採だけでなく、急峻な場所や、構造物付近の伐採時にも役立ちます。

講習日程 : 全7日コース
*講習の参考日程が以下となります。詳細は都度ご連絡いたします。
【日時】各日9:00~17:00 (全7日コース)
- 1日目:高所ロープ作業特別教育
- 2日目:クライミング基礎(樹上に上るまで)
- 3日目:クライミング応用 (樹上の動き)
- 4日目:リギング基礎
- 5日目:リギング応用(広葉樹)
- 6日目:リギング応用(針葉樹)
- 7日目:リギング応用(針葉樹)
講師等
- インストラクター 梶谷哲也(黒滝村森林組合 skyteam)
- コーディネーター 内海美沙(森林プランナー)
対象
チェーンソー使用者。高所伐採を行なっている、または行なっていきたいプロの方 (林業技術者、造園業者、土木技術者等)。なお、ロープワーク伐採は基本2人1組で仕事を行うので、チーム参加をおすすめいたします。
会場
京都府南丹市日吉町内
受講料
180,000円(税込)
募集人数
10名(ただし、1日目は上限なし)
服装
作業着、足元はスパイク付きでないもの(チェーンソーブーツ、トレッキングシューズ、スニーカー、地下足袋など)ヘルメット、軍手、6日目、7日目のみチェーンソー、チェーンソーパンツ
持ち物
飲み物、筆記用具、運転免許証等本人確認できるもの(初回のみ)、あれば高所伐採用道具一式(道具レンタル15000円)、昼食(地元食材を使ったお弁当を800円でご用意できます。)
内容
『講習1:クライミング1 (樹上に登るまで)』
1日目:「高所ロープ作業特別教育」 AM【座学】<ロープ高所作業特別教育> なぜこの法律か 法律の実際の適用状況 PM【座学】クライミング装備の説明、実演 クライミングノット
2日目:「クライミング基礎」 AM【現場】安全について(ヒヤリハット、ハイン リッヒ) スローライン、スローラインからのセッ ト ナチュラル、フォールスクロッチ PM【現場】DdRT(トラディショナル、ブルージック)
『講習2:クライミング応用 (樹上での動き)』
3日目:「クライミング応用 (樹上での動き)」 AM 【現場】SRP PM 【現場】リムウォーク、ダブルクロッチ、リダイ レクト ランヤード
4日目:「リギング基礎」 AM 【座学】安全について(ヒヤリハット、ハイン リッヒ) リギングの力学 リギングノット PM 【座学・現場】リギング装備 リギングシステムについて
『講習3:リギング応用(実習編)』
5日目:「リギング応用(広葉樹)」 AM 【現場】様々なリギングカット PM 【現場】グラウンドワーカーの役割 ポータラップ コントロール(タグ)ライン
6日目:「リギング応用(針葉樹)」 AM 【現場】トップカット(断幹作業)の説明 PM 【現場】トップカットの実習
7日目:「リギング応用(針葉樹)」 AM 【現場】トップカット(断幹作業)の説明 PM 【現場】トップカットの実習
※天候や講習の進捗状況、参加者の状況により講習内容が変更になる場合があります。
受講者特典
- 「高所ロープ作業特別教育修了証」(労働安全衛生法特別教育)が取得できる。(必修講習を受ける必要があります)
- 希望者全員に受講中の動画、宣材写真プレゼント。※2
- 道具の輸入代行が依頼できる。
- 受講後の技術相談、指導が受講者特別価格にて受けられる。(方法:メール、電話、現場)
- 広報ツール、WEBや名刺の作成を受講者特別価格でご提供。(一部補助制度あり)
- 創業支援や助成金活用支援、事務サポートが受られる。
※1 保険は各自ご加入ください。
※2 写真及び動画の使用権は当方と参加対象者の双方に属するとし、使用権譲渡の場合は要相談。